『TO THE MOON』は2011年に公開されたカナダ産のゲームであり、PCやアプリ、Switchにおいて日本語版もリリースされている。
本作は、丁寧に構成された物語に感動する一方、ある程度想像の余地を残して終わる作品である。その余白に、プレイヤーなりの想像を補完して皆それぞれの感動を味わっていると思うのだが、筆者も例に漏れず、感動と共にいくつかの疑問や引っかかりを抱えたままゲームを終えた。そのため、この記事では本作の簡単なレビューと合わせて、その疑問に対する私なりの解釈を書き残しておきたい。
※筆者のプレイ環境はSwitch版です。訳文差があるようなので、他機種版の印象と異なる可能性があります。
※本記事後半の考察パートは盛大なネタバレを含みますので閲覧は自己責任でお願いいたします。

レビュー(ネタバレ少なめ)
あらすじ
海を見渡す灯台の傍にポツンとある家に住む老人・ジョニー。
彼は臨終を待つ身として床に臥せたまま、
医者と家政婦に世話をされながら、静かに最期の時を迎えようとしている。
そんな彼の最期の願いは「月へ行くこと」。
しかし、なぜ彼がそんな願いを持っているのか――
その理由を、本人すら思い出せない。
そんな願いを叶えるために登場するのが、エヴァ・ロザリーンとニール・ワッツという二人のドクター。
記憶を操作するという技術を持つ彼らは、ジョニーの記憶の中に潜り込み、
過去を少しずつ遡りながら“願いの起点”を探していく。
プレイヤーはドクターの視点で、ジョニーの記憶を辿っていくことになる。
晩年の記憶、青春の日々、そして…。
それぞれの場面に散らばった“彼の記憶のカケラ”を拾い集めながら、
一つの願いに込められた真実を少しずつ解き明かしていく。

ゲーム性について
操作は非常にシンプルで、
- マップを歩く
- アイテムを拾う
- キャラクターに話しかける
といった基本動作だけで進行する。
途中に軽いミニゲームはあるものの、進行上の大きな障害になるような難易度ではない。
ゲームとしては“遊ぶ”というよりは、“物語を読むための器”として設計されている。

好きなところ
- 人生の無常さが散りばめられたストーリー
- 静かな世界観(夜にプレイするのをおすすめしたい)
- 世界観を良い意味で中和するエヴァとニールの軽妙なやりとり
- 考察を楽しめる丁寧な物語構成
- プレイヤーを引きこむピアノ音楽

気になったところ
- 移動の遅さ
- アクションや謎解きなどの遊び要素の少なさ
誰向けのゲームか
● 向いているプレイヤー
- ストーリー中心のゲームを好む
- ヒューマンドラマで感動したい
- 4〜5時間で完走できる作品を探している
- 考察しがいのある物語が好き
- しんみりするピアノ音楽が好き
● 合わないかもしれないプレイヤー
- ゲーム性(戦闘・謎解き)を重視する
- 長時間遊びたい
- 自由度の高いプレイ感を求める
短評
“良作映画”という印象である。
ゲーム性はほとんどなく、ほぼ一本道のストーリーだが、精緻に構築された世界観と演出でプレイヤーの心を揺さぶってくる。むしろ物語を楽しむために、ゲーム性を意図的に削っているようにも思える。
未プレイの方にこのゲームのテーマを伝えるならば…
ひとつは「切ない閉塞感」である。
物語の軸となるジョニーの人生には、一見特別な出来事はない。
そこには、ありふれた楽しい思い出もあれば、上手くいかなかったこともある。
良い意味で平凡な人生であるが故に、誰にでも起こりうる後悔やすれ違いを生々しく描写しており、どこか閉塞感を感じる雰囲気が漂っている。
そして、作中の人々に自分の人生を重ねて、彼らに入れ込んでしまう。プレイした私もそうだが、多くの人が本作の切なさ、やるせなさに胸を締め付けられたのではないだろうか。
もうひとつは「結果と過程」になるだろうか。
本作は、“死にゆく老人の夢を記憶の中で叶える”というコンセプトである。
この方法は画期的な幸福支援ではあるが、“終わりよければすべてよし”という考えが根底にあるものである。この考えを否定したいわけではない。ただし、「本当にそれでいいのか?」という問いもまた、この世の中にはあるのである。
この作品は、極端な結果主義ともいえる発想と、それを取り扱う人々を通して、その在り方について、我々に問いを投げかけているような作品になっている。
言い換えるならば、この作品が問いかけているのは──
「幸せとは何なのか」
という問いなのではないかと私は思っている。
そして、この問いには、人の数だけ答えがある。
だからこそ、この物語の結末は、ぜひ自分の目で確かめてみてほしい。
正しいとか間違っているとかではなく、あなたはどう考えるか。
色々な人にプレイしてもらって、色んな感想を聞きたい、率直にそう思っている。
そして、そんな作品だからこそ、自分なりの解釈をこの記事に残しておきたいと思ったわけである。
ここまでがこのゲームに対する短評である。
この先は、もう少し深掘りして、ネタバレを含めつつ本作の物語について考察をしていこうと思うので、未プレイの人はブラウザバックを推奨したい。

⚠️
⚠️
⚠️
⚠️
⚠️
⚠️
⚠️
⚠️
⚠️
⚠️
⚠️
⚠️
※※※ここから先は物語に関する重大なネタバレを含みます※※※
※※※未プレイの場合は閲覧しないことを推奨します※※※
⚠️
⚠️
⚠️
⚠️
⚠️
⚠️
⚠️
⚠️
⚠️
⚠️
⚠️
⚠️
考察(ネタバレあり)
『TO THE MOON』は“幸せの形”にスポットライトを当てる物語である。
そしてその問いは、ジョニーと彼の妻の人生を通して描かれていく。
結論から言うと、ジョニーは記憶の中で月に向かうことで彼の最後の願いを叶える。
確かに彼は幸せな最後を迎えていたのだろう。
しかし、これはあくまで頭の中で幸せな記憶を作っただけであり、いわば“結果の幸福”にすぎない。彼の歩んできた人生は、何も変わっていないのである。
「果たして、これで良かったのか」
考えたプレイヤーもいるだろう。何故なら、ジョニーが月に行くだけでは色々と足りていないものがこの作品には残っているからだ。
今回の考察は、その足りていないもの――
とりわけ、もう一人の人物の視点を中心に掘り下げていきたいと思う。
ジョニーとリヴァー
「月に行く」という願いは、ジョニーが宇宙飛行士になりたかったからとかそんな単純な願いではない。
本作では彼の記憶を遡って彼の人生を振り返っていくわけだが、物語終盤で明かされる彼の幼少期の記憶には非常に重要な情報が眠っているため、彼の抱える背景について取り上げたい。
ジョニー・ワイルズ
「月に行きたい」という願いを持ったまま床に臥せる老人、ジョニー・ワイルズ。
この物語の最重要人物である。
彼には、“ジョーイ”という名の双子の兄弟がいた。そして原因は分からないが、母親からはジョーイの方が可愛がられる傾向にあったようだ。
そのことにジョニーは不満を感じていたのだが、ある時、大きな事件が起きる。
ジョーイが母親の運転する車に轢かれて亡くなってしまうのだ。
兄弟の死、というのは幼少期のジョニーからすればそれだけで大きなショックだろう。
しかし、追い打ちをかけるように母親が精神を病み、自身の罪から目を背けるようにジョニーをジョーイと呼びはじめるようになる。
ジョニーはこの状況に耐えられなかったのだろう。
結果的に彼は、薬の影響によって幼少期の記憶を失ってしまう。
そしてこの時、彼は不幸にも、“大切な人との約束”という重要な記憶も消してしまったのだ。
その大切な人というのが──
“リヴァー・ワイルズ”
──生涯を添い遂げた彼の妻である。
そして、この記憶障害が二人の間に深いすれ違いを生んでしまうのだ。
このすれ違いこそが、彼の最後の願いに繋がる“未練”なのである。
では、二人の間に何があったのだろうか。
ということで、この物語の二人目の重要人物“リヴァー・ワイルズ”という女性について掘り下げていこう。
リヴァー・ワイルズ

ジョニーの妻、リヴァー・ワイルズ。
プレイした方には理解していただけるだろうが、彼女は一言で言えば“独特”である。
ウサギの折り紙を折り続けたり、灯台の傍に家を建てることに拘ったり、周囲との協調よりも自身の内部論理を優先する姿が目立つ。
作中では障害と表現されているが、この独特さは彼女が生まれつき周囲との感覚がかみ合いにくい発達特性を持っているためであり、ジョニーや周囲の人々から真意を理解されないことも少なくない。
また、彼女自身も周囲に馴染めない感覚を幼少期から抱えており、そのことに対する悩みを彼女なりの言葉で形にする場面もあったりする。
彼女はジョニーの記憶の中に登場し、ジョニーと出会い、結婚し、やがてその人生を終える。
そして、実は二人は幼少期に邂逅しているのだが、その“始まりの日”についての記憶を、ジョニーは失ってしまっている。
そして、その忘れられた“始まりの日”の中には、「月に行きたい」という願いの起点となった約束と、リヴァーにとって何よりも“大切だった記憶”が、眠っているのだ。
始まりの日
とあるお祭りの日の夜、幼少期のジョニーは家族の輪から離れるようにして森の奥へ月を見に来ていた。そこへ同じ目的で現れたのがリヴァーだ。
二人は月を見上げながら、少しずつ言葉を交わす。
最初に出てくるのはお互いの「名前」の話。リヴァーは自分の名前をからかわれていること、そして「みんなと同じになりたい」と願っていることを、ぽつりぽつりと語る。
リヴァー「一度でいいから…みんなと同じ名前になりたい」
対してジョニーは、ありふれた自分の名前に不満を抱き、「みんなと同じなんてつまらない」と返す。二人は正反対の悩みを抱えながらも、不思議と会話が噛み合っていく。
やがて二人は夜空にウサギの星座を描き、リヴァーは星々を「灯台」に見立てて語る。
リヴァー「灯台たちにできるのは、遠くで、光ることだけ。」
リヴァー「いつか…私は、あの子たちの中のだれかと、友だちになるから。」
そして最後に、二人は一年後の再会を約束するものの、リヴァーは「忘れてしまったら」「迷子になるかも」と不安を口にする。そんなリヴァーにジョニーは反射的にこう返す。
ジョニー「大丈夫!その時は、月で待ち合わせだ!」
これがこの夜に交わされたやり取りである。
ジョニーの「月に行きたい」という願いは、この時の「月で待ち合わせ」から導かれたものである。だが、皮肉なことに、この後、ジョニーはこの約束を含む幼少期の記憶を失ってしまうのである。

二人のすれ違い
ジョニーは結局、約束を交わしたことを忘れたままリヴァーと再会し、結婚する。
この作品は老年のリヴァーが亡くなった2年後の世界からスタートするのだが、この時点においてもジョニーは思い出すことが出来ていない。
ただ、理由も分からず「月に行きたい」という願いだけを抱えているのだ。
最終的にジョニーは記憶の世界で月に向かうわけだが、その方法は持っている記憶を“二人で月に向かった”という記憶に改編するという方法である。
それは、彼にとっては確かに救いであり、幸福な結末であったのだろう。
しかし同時に、それは彼の人生が「本来歩んだものとは別の形へと書き換えられた」ことも意味している。
この点に、違和感を覚えたプレイヤーもいるのではないだろうか。
──そして、彼が願いを叶えた一方で、リヴァーはどうなのだろう。
彼女は既にこの世界にいない。
彼女は月に向かうことが出来なかっただけでなく、約束をした相手が約束を思い出すこともないまま、そして忘れられた理由を知ることもなく、この世を去ってしまっている。
そして、彼女はジョニーがあの日の約束を覚えていないことを間違いなく気にしていたのだ。
リヴァーは無念を抱えたまま亡くなったのではないか…?そう思わずにはいられない。
ただ、だからと言って、簡単にリヴァーを不憫だと断じるのも、私は違うと思っている。
彼女がジョニーとどのような気持ちで向き合ってきたのか、それをもっと考えてみたい。

リヴァーは何を望んでいたのか
まず、“そもそも、リヴァーは月に行きたがっていたのか?”という問いがある。
厳密にいえば、リヴァーが欲したのは「月」そのものではない、と私は思っている。
──では、彼女が一体何を欲していたのか。
彼女が終始直接的な表現を避けていたことから、これをどう考えるかが、この作品で最も意見の分かれるところではないだろうか。
果たして、彼女は本当に無念のまま亡くなっていたのか。
彼女は一体何を考え、何を望んでいたのか。
これを読み解くため、多くを語らない彼女の行動を細かく振り返っていきたい。
彼女の行動
彼女の印象的な行動はいくつかある。
🟦1. カモノハシのぬいぐるみ
“始まりの日”において幼いジョニーがリヴァーに贈ったカモノハシのぬいぐるみは、二人が再会する前からずっと彼女の手元にあった。
作中を振り返っても、リヴァーの周囲には最初から最後まで、いつもこのカモノハシが寄り添っている。
この描写から、彼女が “始まりの日”を強く特別視していた ことは明らかだ。
🟦 2. 灯台(アーニャ)
幼い頃、「灯台のどれかと友達になる」と語っていたリヴァーにとって、この灯台はまさに“友人”だったのだろう。
彼女は灯台としての役目を終えたこの場所にアーニャと名を与え、自身の延命を拒否してまで、そのそばに家を建てようと願い続けた。
結婚式の場所もアーニャのそば、そして彼女の墓も同じ場所に作られている。
ただし、ジョニーの視点では「なぜここまで灯台にこだわるのか?」が最後まで分からない。
(記憶を封じているのだから当然だが。)
🟦 3. フットバッグ
ジョニーの記憶の中には、ジョニーがリヴァーに最初に惹かれた理由を語るシーンがある。彼女の独特さが眩しく、関わることで“なりたい自分に近づける”と感じた──そんな説明だ。
この話を聞いたリヴァーは、ジョニーが“始まりの日”を覚えていないことを悟る。
そしてフットバッグを見せ、「これを投げられる?」と促した。
これを見れば思い出してくれるかも──
そんな淡い期待を込めていたのかもしれない。
だが、ジョニーは思い出す様子もなくフットバッグを遠くまで投げてしまう。
この時のリヴァーは飛んでいくフットバッグをただ見つめるだけであったが、内心どう感じていたのか。──正直推し量り切れないものがある。
その出来事を境に、リヴァーはウサギの折り紙を折り始めるようになる。
投げられたフットバッグは、この後、作中で回収されず行方知れずになる。
🟦 4. ウサギの折り紙
最も象徴的なアイテムがこれだ。
お腹だけ黄色、その他は青い紙を使ったウサギの折り紙。
その配色は、“始まりの日”において、二人で描いたウサギの星座の再現である。
リヴァーはただ黙々と折り続ける。
ジョニーに意図を聞かれても答えず、遠くを見るような目で「どう思う?」とだけ尋ねる。
彼女は、言葉こそ少ないものの、一見独特とも呼べる行動の数々で何かを伝えようとしていた。
では次は、これらの行動から読み取れることについて考えていきたい。




彼女の思い
彼女の行動を振り返ると、やはり“始まりの日”のことを思い出してほしい、という点は一貫してそうである。
ただ、“それが何故か”まではまだ分からない。
ここで、彼女の生来の特性を踏まえつつ、“始まりの日”のことを深く掘り下げていきたい。
リヴァーは幼少期の頃から「周囲に溶け込めない自分」にコンプレックスを抱いていた。診断を受ける前だった彼女は、周囲には“変わった子”だとからかわれていたのだろう。
ここで、ジョニーと初めて出会ったシーンの彼女のセリフを振り返りたい。
リヴァー「みんな、他の灯台のこと、見えてる。話したいと思ってる。」
リヴァー「でも、できない。遠すぎて、他の灯台たちの声は、届かない。」
夜空の星々を灯台に見立てて語られたセリフだが──
これは星の話であると同時に、リヴァー自身の話でもある。
そして、このセリフ──
リヴァー「私は、あの子たち(灯台)の中のだれかと、友だちになるから。」
一見飛躍した発言にも思えるが、彼女が星や灯台に自身を重ねていたのであれば、筋が通る。
そのほかにも、
リヴァー「一度でいいからみんなと同じ名前になりたい」
とも語っており、これらの発言は、“今の自分には居場所がない”という感覚を、彼女なりの言葉で表現したものだと考えられる。
──そして、そんな彼女の前に現れたのが、ジョニーである。
リヴァーと初めて出会った頃のジョニーは、没個性を象徴するかのような「ジョン」という名前を背負い、家庭では、ジョーイの存在にかき消され居場所を奪われた存在であった。そんな境遇から、“特別になりたい”というコンプレックスを抱えていた。
ジョニーとリヴァーには、一見対極のようでいて、一つの共通点がある。
──二人とも“居場所”を欲していたということ。
リヴァーは周囲と同じじゃないことで、
ジョニーは周囲と同じにされることで、
二人とも“居場所”を失っていたのである。
自分の持たないものを持ちながら、それでも同じように苦しんでいる──
リヴァーは、そんなジョニーの姿にどこか救われていたのではないだろうか。
彼女がジョニーに心を許したのは、自分とは違う立場にいながらも、同じ方向の孤独を抱えた少年だったからだ。
奇しくも、お互いのコンプレックスが、相手に“居場所”を提供していたのである。
――不思議に思わなかっただろうか。
「一度でいいから皆と同じ名前になりたい」と発言するほど、協調できない自分にコンプレックスを感じていたはずの彼女が、最後までありのままを貫いていたことを。
それは、このやりとりがありのままの彼女を肯定したことが一因なのではないかと、私は思っている。
リヴァー「みんなと同じ名前。何がダメ?」
ジョニー「だって…つまんないよ」
ジョニー「みんなと同じなんて、意味なくない?」
そしてリヴァーは…
そんなジョニーからもらったカモノハシだから、ずっと持って歩いた。
そんなジョニーと作った星座だから、折り紙を折り続けた。
そんなジョニーと交わした約束だからこそ、大切にしていた。
――のではないだろうか。
とすれば、やはり彼女の望みは
「ジョニーと月に行くという約束を果たす」よりも
「二人にとっての特別な“始まりの日”のことを思い出してほしかった」の方が近かった。
そう考えられるのではないだろうか。
彼女が大切にしていたものも、彼が取り戻したものも、単なる約束ではない――
リヴァーにとっては“居場所”そのものであり、ジョニーを特別な相手たらしめた、二人の関係の原点であったのだ。

彼女の幸福
と、ここまで考察したうえで元も子もないことを述べると――
そもそもジョニーは、“月に行くことが出来ない”、というよりは“思い出すことができない”ところで止まってしまっていた。
そう、仮にリヴァーが“思い出してくれるだけで良い”と思っていたのだとしても、間に合ってはいない。
とすれば、結局、彼女は不憫なままである。
素直にこの結末を受け入れるなら、これはやるせない結末なのだ。
――しかし、本当に救いはないのだろうか?
正直、ここからは私の妄想なのかもしれないが、ひとつ気になることがある。
それは、死期が迫るリヴァーに悲壮感がなかったこと。
最後まで、ウサギを折り続けていた彼女が諦めていたわけではないだろう。
彼女には、彼女なりに考えていることが何かあったのではないだろうか?
ということで、ここからは晩年の彼女が何を考えていたのか、掘り下げていきたい。
彼女の心を読み取るために、重要なセリフがある。
リヴァー「私は、幸せになる」
死期が迫るリヴァーが、治療を拒否しながらジョニーに語ったセリフである。
ここで注目したいのは、「幸せになりたい」ではないことである。
──ここから、ひとつの推論が出来ないだろうか。
彼女にとっての幸せは、“与えられるもの”ではなく“自分自身で選びとるもの”だったのではないか。
そしてその選択とは“自分の大切なものを守ること”だったのではないだろうか。
リヴァーにとって大切なのは、他ならぬ“始まりの日”の思い出だ。
彼女にとって、目の前にいるジョニーは確かにジョニーなのだが、最も大切なものが欠落しており大切なジョニーとは少しずれた存在だったのだろう。
しかし、大切な思い出を忘れられてしまったリヴァーは、ジョニーを責めるわけでもなく、悲嘆に暮れるわけでもなかった。
ウサギの折り紙、灯台、カモノハシ──
彼女にとっての大切な思い出を守り続けていた。
本来、思い出してもらうことを優先するのであれば、他にも建設的な行動があるはずだ。
さらに言えば、新しい思い出を積み重ねるという割り切り方だってあったはずである。
しかし、彼女はそうしなかった。
であれば、この行動には思い出してもらう以外の彼女なりの考えがあるように思える。
もちろん最初は思い出してもらおうとしていたのかもしれない。
しかし、ジョニーが思い出してくれるかどうかは、結局ジョニー次第なのである。
彼女の行動に結果が必ず答えてくれるとは限らない。
だからこそ、彼女は自分なりにできることをやることにしたのだろう。
慈しむように、彼女なりの方法で「特別だった二人の時間」を守っていたのだ。
それらは、ジョニーに“思い出させる”ための行動という意味以上に
“始まりの日”という思い出を、この世界から消さないための行為だったように見える。
一見独りよがりの行動に見えるかもしれない。
他にも建設的な方法はなかったのか…。そう思うかもしれない。
しかし、彼女のそんなありのままを肯定したのは他ならぬジョニーなのである。
もちろん、結果こそ得られないまま彼女は亡くなってしまう。
しかし彼女は、たとえ上手くいかなくても、最後まで自分を曲げなかった。
ジョニーが肯定してくれたありのままの自分であり続けた。
だからこそ、「幸せになる」だったのだ。
きっとそれこそが、リヴァーにとっての“幸福論”なのだろう。
だとすれば、リヴァーを不憫だと断じるのは、早計なのではないだろうか。
あくまで推論ではある。
しかし、可能性のひとつとして、私はそう信じたいと思っている。

イザベルとの対比
もし、リヴァーが別の生き方を選んでいたとしたら、どうなっていただろうか。
作中には、その“もうひとつの可能性”を体現する人物がいる。
それが、イザベルである。
イザベルもまた、リヴァーと同じ特性を持ちながら生きている。
しかし彼女は、周囲に合わせ、自分を偽ることで社会に適応しようとした。
その結果として、彼女は「生きづらさ」を抱えている。
一方でリヴァーは、イザベルのような器用な生き方を選ばなかった。
この対比がある以上、リヴァーの「私は、幸せになる」という言葉を、
単なる強がりや自己暗示として片づけることはできないのではないだろうか。
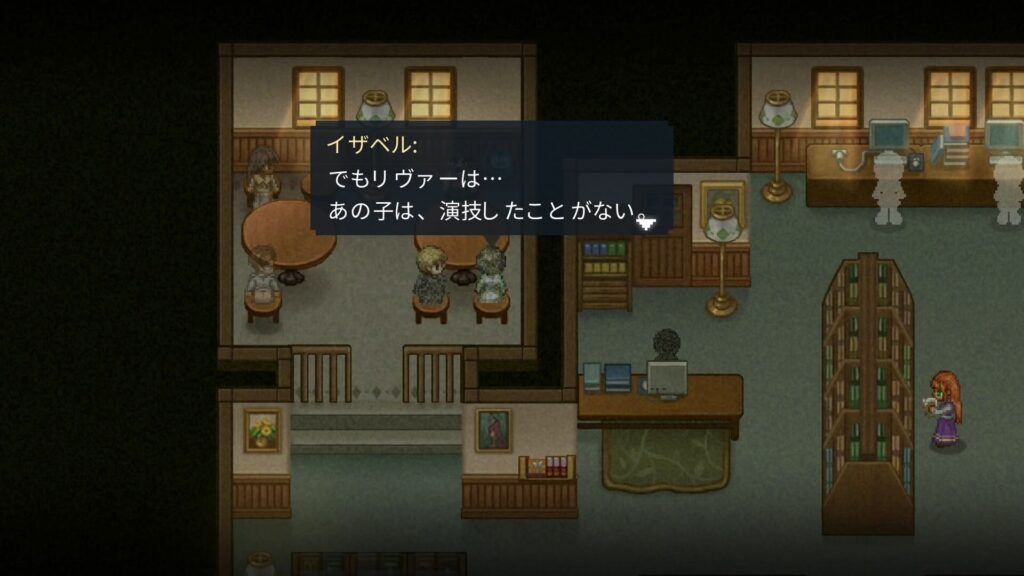
記憶の上書きについて
ジョニーは最終的に自身の本当の記憶を上書きしてしまう。
おそらくリヴァーは“始まりの日”を思い出してほしいとは思っていたはずだが、他の記憶を消して、とまでは思っていなかったはずだ。ここは、個人的には最後まで引っかかっていた部分である。「これまで生きてきた記憶を旦那さんが忘れちゃってるけど大丈夫…?」と。そもそも彼女が死んだあとのことなので観測しようがないという話もあるが。
ただ、彼女には“新しい思い出の積み重ねよりも、特別な思い出を守ることを選んだ”という前提がある。
そして、“彼女の在り方そのもの”が彼女にとっての“幸福”だったとするならば、仮に他の記憶を忘れられたとしても、そんな結果は関係ないのかもしれない。
もちろん、はっきりした答えはリヴァーにしか分からない。
ただ、ここまでの推測を踏まえるならば、例えジョニーの最期を知ったとしても、案外彼女は気にせず、“始まりの日”を思い出してくれたことを喜んでくれるのかもしれない。
何故この物語は『TO THE MOON』なのか
ここからは、別の角度から気になるところを掘り下げていきたい。
月はいつだって空に浮かぶ
そもそも何故二人は、月という“気軽には行けない場所”で待ち合わせをしてしまったのか。
待ち合わせ場所というのは、本来お互いにとって分かりやすく、かつアクセスしやすい場所に設定するものである。
ならば、ここには直接的な意味以上のものがある、そう考えた方がいいだろう。
約束の流れを振り返ろう。
本来は「また一年後にこの場所で」という約束だった。
しかしリヴァーはそこで、ふと不安を口にする。
リヴァー「でも、もし忘れちゃったら、迷子になったら…」
この場面でリヴァーは心を許せると思った相手に忘れられてしまうという不安を抱えていたのではないだろうか。
ジョニーが、どこかへ行ってしまう…
そして、きっともう出会えなくなる…
そして、恐らくジョニーは、この不安を直感的に感じ取ったのだと思う。
そこで反射的に出た言葉が、「忘れたら、月で待ち合わせ」である。
月というものは、あの場面においてもっとも不変性が高い。少なくとも二人が生きている間は、いつだって、どこにいたって、変わらぬ姿でそこにある風景なのだ。
彼が伝えたかったのは、待ち合わせの場所というよりも、
「仮に忘れてしまっても、どんなに遠くにいっても、長い時間が経っても、きっと君を、そしてこの日のことを思い出す。」
――そんな宣言に近かったのだろう。
だからこそ、たとえ記憶が失われても、
月だけは二人をつなぐ“最後の糸”として残り続けたのかもしれない。
そしてリヴァーも、きっとジョニーの発言の意図を汲んでいた。
だから、最後まで諦めずに思い出してもらおうとしたのだ。
“始まりの日”のことを、教えるのではなく、ジョニーに思い出してもらいたかったのだ。

その願いは誰のものか
もう一つ、疑問がある。
――なぜ、記憶を失くしたはずのジョニーは最期に「月に行きたい」と願えたのか。
ジョニーは最終的に、記憶に潜り込む技術を応用した裏技のような方法で失った記憶を取り戻す。それほどの方法を用いなければ思い出せないほど、強固に記憶を封じ込めていたのだ。
それを考えると、リヴァーの遠回しなメッセージがジョニーに届かなかったのは、仕方のないことである。
だから、本来は思い出せるはずがない。――はずなのだが。
これはあくまで私の推測、いやいっそ願望かもしれない。
リヴァーは最後まで“始まりの日”のことを守り続けていた。
そして、「ジョニーがいつか“始まりの日”を取り戻しますように」と、延命すら遠ざける思いで祈っていた。
そんな健気で不器用な精一杯の行動が、最期にやっと通じたのかもしれない。
記憶を呼び起こすとはいかなかったが、彼女の願いはきっと記憶すらも飛び越えて、ジョニーの体を突き動かしたのだ。
そして、彼女が最後まで、希望を持てたのは――
「必ず思い出せる」
――あの日のジョニーがそう宣言したから。なのである。
とするならば、「月に行きたい」と願ったのは果たして、
ジョニーだったのか、リヴァーだったのか…、その両方なのかもしれない。
そう考えると、『TO THE MOON』とはジョニーの夢というだけではなく、
二人の間を繋いだ願いの名前だったのかもしれない。
物語の結末
あの結末をどう捉えるかは、プレイヤーに委ねられているのだろう。
であれば私は、なるべく素敵な結末にベットしたい。
あれは、決して悲しい結末ではない。
そう、信じたいと思う。
叶ったのはジョニーの夢だけではない。
「幸せになる」と誓ったリヴァーの、祈りにも似た願いが叶った――
彼女の祈りが、小さな奇跡を起こした。
そう信じたくなる気持ちそのものが、この物語の用意した幸福なのだろう。

おわりに
この物語に対する私の印象は、時間が経つにつれて変化していった。
最初はただ「良いEDだ」と直感的に思っていた。しかし少し冷静になると、リヴァーの無念は何ひとつ解決されていないのでは?と、胸に引っかかりが生まれた。この結論に至るまでに、解釈を迷ったところや、筋が通るよう情報を取捨選択した部分もある。それでも細部の描写を追うたびに、「いや、救いはあるのかもしれない」と思わせてくれる。もしかすると、この記事を書き終えたあとで、また印象が変わるかもしれない。だから、ここまで書いてきたことはあくまで“現時点での私の解釈”だ。
ここまで色々考えたが、身もふたもない結論を言うと
――この作品の解釈はプレイヤーによって大きく異なるだろう。
私の中ですらコロコロと印象の変わる物語なのだから、受け取る人が変わればまったく違う物語になるだろう。どの解釈が正しいというわけではなく、プレイヤーの好きに解釈していい、という懐の広さを作品そのものが持っている。
そして、それもこの作品の魅力なのだと思う。
だからこそ、色んな人に触れてほしいし、プレイヤーとしての感想を形に残したい――そう自然と思わされる作品だった。
この記事で取り上げきれていない要素はたくさんある。ただ、あまり風呂敷を広げすぎても仕方がないので、最後にこの作品の自分なりの総括を記して、ここで筆を置こうと思う。
ジョニーは、本当の記憶こそ失ってしまうが、改編された夢の中で幸せな眠りについた。
一方、リヴァーは、結果こそ得られなかったかもしれないが、彼女なりの姿であり続けることで幸せを目指した。
ジョニーは「結果の幸せ」、リヴァーは「過程の幸せ」というそれぞれの答えに行きついたのである。
どちらが正しいとか間違っているとかではない。
幸せの形は人それぞれで、この作品は二人の対比を通して、我々に問うているのだ。
「あなたはどう思いますか?」と――。
ここまで読んでいただき、ありがとうございました。


コメント